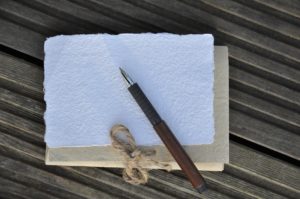相続手続きの期限と流れを知っておこう!期限が過ぎたらどうなる?

遺産相続の手続きには、さまざまなものがあります。
「死亡届はいつまでに出せばいいの?」
「相続の放棄は?」
「相続税の申告は?」
葬儀や法要のあわただしさで、遺産相続の手続きにまで手が回らないのが現実かもしれません。
ついうっかりしていて、期限までに適切な手続きをしなかった場合、どんなペナルティがあるのでしょうか?
この記事では、しっかり押さえておかなければならない遺産相続の手続きのスケジュールについて解説します。
Contents
相続手続きの期限を一覧表で紹介!相続手続きスケジュール
相続手続きにはそれぞれ期限があります。
期限はいつから始まるかというと、「被相続人が亡くなったことを知った日」から。
ここでは知っておいて損はない、大切な相続手続きの流れてと期限を一覧表で紹介します。
相続手続きの流れと期限
| 手続きの流れ | 期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 7日以内 | 死亡診断書を市町村に提出 |
| 相続の放棄・限定承認 | 3カ月以内 | 相続放棄や限定承認を希望する場合は家庭裁判所に申請 |
| 所得税の申告(準確定申告) | 4カ月以内 | 1月1日から死亡した日までの所得を計算し、税務署に申告と納税をする |
| 遺産分割協議 | 期限なし※ | 相続人全員で遺産分割の話あいをし、遺産分割協議書に実印を押印する |
| 相続税の申告・納付 | 10カ月以内 | 遺産を相続した人は相続税の納付をする |
| 相続財産の名義変更 | 期限なし | 不動産の相続登記や預貯金などの名義変更をします |
| 遺留分の減殺請求 | 1年間 | 相続を知ってから1年以内に家庭裁判所に申請します |
【重要!】相続の放棄と限定承認は3カ月以内に済ませる
被相続人が亡くなってから、何を置いても先にやらなければいけないことがあります。
まずは被相続人が亡くなったあと7日以内に提出する「死亡届」です。
葬儀や法要であわただしいこととは思いますが、相続についての手続きもおざなりにしてはいけません。
相続に「どんなもの」が「どのくらい」あるのか?
相続人は「だれ」なのか?
相続手続きには期限がありますから、このころからしっかりと把握しておいたほうが、あとあと慌てなくて済みます。
ここでは3カ月以内に必ずやるべきことについて解説します。
3か月以内に必ずやるべきこと
- 遺言書の検認
- 相続人の確認
- 遺産内容を把握する
まずは被相続人が遺言書を遺しているかどうか、できるだけ早いうちに確認します。
もし手書きの遺言書が見つかった場合は、開封せずにすみやかに家庭裁判所で検認※の手続きをしましょう。
検認とは
相続人に対して遺言書の形状や訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きのこと。
検認について詳しい解説は「自筆証書遺言の検認とは!開封したら無効?手続きの手順などを徹底解説」をお読みください。
検認手続きには法定相続人全員の戸籍謄本を用意する必要があります。
法定相続人についての詳しい解説は、「【図解】5分でわかる!法定相続人の範囲や順位、それぞれの配分とは」をお読みください。
次に相続される財産のなかに、不都合なものはないか必ず確認しましょう。
ここでもし被相続人に多額の借金や借入金があったり、連帯保証人などになっていることが発覚した場合、そのままにしておくと負の遺産まで相続することになってしまいます。
もし借金などの負の遺産が発見された場合、必要になる手続きが「相続放棄※」です。
相続放棄とは
被相続人の財産を継承する権利、すべてを放棄すること。
このとき相続放棄さえすれば、配偶者や子供は被相続人のプラスの財産を相続できないかわりに、借金や連帯保証人の責任も引き継がなくてよくなります。
これを知らないでいると借金まで相続することになり、負債が多額にのぼる場合は自己破産に追い込まれるという恐ろしいケースもあるんですよ。
また負の遺産が発見された場合の対処法に、「限定承認※」という手続きもあります。
限定承認とは
プラスになる財産の範囲内で負の財産を継承すること。
被相続人の財産のうち、あきらかに負の財産のほうが少ないと判断される場合は、相続放棄してしまうよりも限定承認をしたほうが結果的にトクという可能性もあります。
「相続放棄」と「限定承認」は、自分の財産にかかわる重要な手続き。
申し出がなければ認めてもらえませんので、必ず3カ月以内に手続きをするようにしましょう。
被相続人の所得税の申告(準確定申告)を4カ月以内に行う

そのあともゆっくりしているヒマはありません。
亡くなった方の所得を、税務署に申告しなければならない期限は、相続開始後4カ月以内です。
え?死んでいるのに確定申告?
と思われる方もいるかもしれませんね。そうです、本人はなくなっているのでできませんが、誰かが代わりに確定申告をする必要があるのです。
通常の確定申告は大体2月中旬から3月中旬に済ませますが、亡くなった方の所得の申告と納税は、「準確定申告」といい、通常の確定申告の日付通りではありません。
相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額、および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。(国税庁ホームページより抜粋)
準確定申告が必要な人は、次のとおりです。
準確定申告が必要な人とは?
- 自営業者
- 不動産などの収入があった人
- 給与所得が2,000万円以上あった人
- 2カ所以上の会社から所得をもらっていた人
- そのほか給与以外に所得があった人
- 高額医療費控除などの控除が受けられる人 など
相続人がふたり以上いる場合の申告方法や、被相続人の事業形態によって確定申告書の様式が違うなど、申告方法にも注意が必要です。
迷ったら管轄の税務署に問い合わせてみてください。
なかなか面倒な手続きではありますが、準確定申告の手続きを怠ると、「申告漏れ」「脱税」と判断され、重い追加徴税が科せられたり、無申告加算税や延滞税が発生する恐れがあります。
加算税や延滞税は「申告間違い」「知らなかった」としても免れないペナルティーなので、かならず忘れずに正確な手続きをしましょう。
遺産分割協議に期限はない?しかし放置はNG
相続がある場合、相続人の間でもたれる相続の話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議にとくに期限はありません。
しかし期限がないからといっていつまでも先延ばしにしていいものではありません。
遺産相続が終わらないうちに、また親族が亡くなり次の相続が発生してしまう、それも終わらないうちに次の相続が発生してしまう・・・。
このようなことになると、相続人をたどるのも大変な作業になってしまいます。
もしもモメるようなことになれば長引くことも考えられますから、遺産分割協議はできるだけ速やかに話し合いの場を持つほうがいいでしょう。
ただここで注意すべきなのは「相続税の申告が必要になる場合※」です。
相続税の申告が必要になる場合とは?
遺産にかかる基礎控除は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、これを上回らないならば、相続税の申告は必要ありません。
もし相続税の申告が必要になる人の場合、遺産分割協議は「相続税の申告と納付」の期限までには済ませる必要があるのです。
・・・・え?
でももし遺産分割協議でなかなか合意しなかったら、相続税の申告も延期できるんでしょ?
いいえ、相続税の申告や納税は延期することはできません。
ではどうすればよいのでしょうか?
対処法は、次の章をお読みください。
相続税の申告と納付は待ったなし!相続税の申告と納税の期限は10カ月以内

相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から「10カ月以内」に行うこととされています。
相続税の申告期限は納付期限と同じ、10カ月以内です。
たとえば1月5日に亡くなった場合、その年の11月5日が申告・納税の期限になります。
期限までに申告と納税をしなかったり、実際の額より少なく申告した場合、加算税や延滞税というペナルティーが課せられます。
これはたとえこのルールを知らなかったとしてもペナルティーは免れませんので、注意が必要です。
また相続税は「一度に」「現金」で納税するのが原則ですが、延納や物納も認められています。
延納制度と物納制度とは?
何年かに分けて納付することを延納、相続などで取得した財産のまま納付することを物納といいます。相続税は現金以外にも納税方法が選べます。
相続税の申告期限に間に合わないときのふたつの対処法
相続税の申告と納付期限は、相続開始から10カ月以内と決まってます。
これは決して伸ばすことができません。一日でも遅れると延滞税が課されるため注意が必要です。
しかしもし相続税の納付期限までに遺産分割協議がまとまらなかったら・・・どうなるのでしょうか?
「相続人同士でモメてしまい遺産相続が進まない」
「時間を要する土地や建物の評価に手間取り、申告書が作成できない」
このようなときの対処法は、次のふたつです。
相続税の申告期限に間に合わないときの対処法
- 相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出
- 相続税をいったん多めに申告する
相続の取り分でモメている場合、いったん法定相続分で申告します。
その申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出すると、向こう3年間以内に遺産が正しく分割された場合、小規模宅地等の課税価格や配偶者控除の特例も受けることができます。
さらに3年が経過してもまだ相続の分割が済んでいないときは、相続裁判の係争中だったりやむを得ない理由がある場合のみ、「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出すれば認められます。
また土地や建物など査定するのき時間がかかり申告書の作成が間に合わないときは、相続税をいったん多めに申告するようにしましょう。
申告した金額に誤りがあり、万が一「過少申告」に該当すると、「修正申告書」を作成しなければならず、これも加算税や延滞税の対象となります。
一方で、「多めに」相続税を納税していた場合は、相続税の申告期限から5年以内であれば「更生の請求※」を申し立てることができるのです。
更生の請求とは
払いすぎた税金を払い戻してもらう(還付請求)の手続きのこと。
税務署が調査をし更生の請求が認められれば、払いすぎた相続税は還付されるというわけです。
税金については専門家でなければなかなか判断が付かず、難しいことも多いことでしょう。
迷ったら管轄の税務署に問い合わせる、または税理士に相談することをオススメします。
税理士探しを無料サポート!メールで相談できる税理士ドットコム ![]()
金融機関の通帳・不動産はどうなる?相続財産の名義変更には期限がない

金融機関や不動産登記の名義を変更するのに期限はありません。
手続きをしなくても、特にペナルティーはありません。
しかしそのままの状態で長期間放置されていても問題は解決しませんし、いずれはやらなくてはいけない手続きなので、できることなら先延ばししないことが大切です。
遺留分の減殺請求は相続があったことを知ってから1年以内に
相続の手続きにおいて期限があるのは、遺留分の減殺請求※です。
遺留分の減殺請求とは
侵害された遺留分の返還を求める申し出のこと。一定の法定相続人に認められた最低限の取り分である遺留分は、たとえ遺言書でも侵害することができません。
遺留分の減殺請求について詳しい解説は「遺言書でも侵害できない法定相続人の遺留分とは?範囲と順位を解説!」をお読みください。
遺留分の減殺請求は、相続があったことを知ってから1年間行使しなければ無効となってしまいます。
また相続があったことを知らなくても、相続開始から10年が経過すれば時効になります。
もし遺留分だけでも取り戻す意思があるなら、できるだけ早く行動しましょう。
相続手続きの期限が過ぎたら大変!余裕を持った行動を
この記事では相続手続きの各種期限について解説してきました。
そのなかでも絶対に忘れてはならない相続手続きの期限は、次の3つです。
- 7日以内に提出する死亡届の期限
- 3カ月以内に提出する相続放棄・限定承認の期限
- 10カ月以内に済ませる相続税の申告期限
※ただ、相続財産が「遺産にかかる基礎控除」より少ない場合は、相続税の申告は不要です。
これら3つの期限はとても大切なので、必ず心に留めておいてくださいね。
特に相続税の申告についていえることですが、一番よくないことは「どうすればいいのかよくわからない」からといって無申告のまま放置してしまうことです。
遺産相続で資産が増えたと喜ぶ前に、今一度立ち止まり、やるべきことが残されていないかもう一度確認してみることをおすすめします。